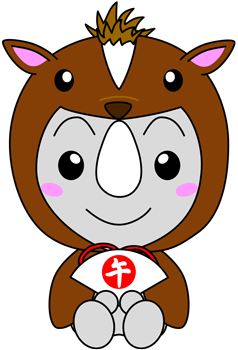こんにちは。サイちゃんです。
こんな記事が流れてきました。
こんな問題を小学生が解くとき。
計算の順序は理解できているのに、答案が以下のようになってしまう子がいます。
25+(15-3)×2+18÷3-2=12×2=24+25=49+6
=55-2=53
イコールの意味に気づいていない子も多いです
いえ、小学生に限らず、中学生にもいます。
これ、どうでも良いようで、どうでもよくない内容。
この話を読み解くとき、「=(イコール)」とは、なんぞや?という話になると。
記事では、「さぁ、計算しますよ!」という意味と書いていますが、ちょっと違うと思っていて、
以前、「「答えは」という意味ではないんだよ」と塾長が指導したら、「えっ?!違うの?」と塾生が反応していたことがありました。
ただ、結局、「=(イコール)」の意味が分かってないのは、間違いないです。
この問題をひも解くにあたり、ちょっと思うのは、省エネを目指しているという点。
記事にも書いていますが、無駄なものを書きたくないという気持ち。
塾としては、等しくないんだから「=」を書くなと指導します。
でも、「=」は書くんだよね。面倒なら、「=」も省けば良いのに。
ウチの塾でも、どうしても、取り出して計算したいなら、このように書くことを推奨しています。
25+(15-3)×2+18÷3-2
12×2=24
25+24=49
18÷3=6
49+6=55
55-2=53
でも、これでも、同じ数字を2回書かなければいけないので、面倒です。
だいたい、こういう主張をしてきます。
メモ書き程度に収めておけば良いのですが、解答として書いちゃうから、変なことになってしまうんです。
結局のところ、面倒くさがってサボるから、演習量が減って出来るようになりません。
また、面倒くさがって省略するから、ミスが誘発され誤答になります。
出来るはずのことも、余計に出来なくなっています。
こういう悪循環をするのが、出来ない子の特徴だったりもします。
結局、そこに着地するのかな?と思ったりします。
急がば回れと言います。面倒だからとサボると、もっと面倒なことになってしまいます。
サボらず、丁寧に取り組んでくだサイ。