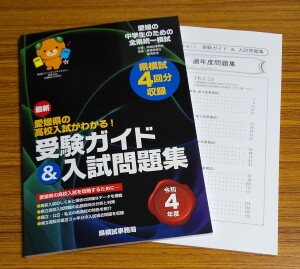こんにちは。サイちゃんです。
広辞苑から、ハッピーマンデーが消えるという情報を入手した1年生。
「ハッピーマンデーって何?」と。
ハッピーマンデーが辞書に載っていたことに、まず驚きですが、
さらに、役目を終えた言葉になってしまったことにも驚きです。
さて、ハッピーマンデーとは、成人の日のように、月曜日を祝日にし、3連休をつくろうというもの。
誰が幸せになれるのかわかりませんが、連休だから、ハッピーなのかな?
そんなハッピーマンデー、今でこそ当たり前になりましたが、開始当初は、色んな所で混乱と不具合が多かったです。
そもそも、この制度は、月曜日に祝日が集中してしまいます。
そうなると、曜日で動いている、例えば、塾とか学校では、問題が起きます。
分かりやすいのは、週に1回しかない家庭科とか、音楽の時間が月曜日にあるとすると、授業がしょっちゅう飛ぶことになります。
これは、困ったちゃんですね。
じゃぁ、月曜日には、そういう授業を組まなければ良いじゃないかと思うかもしれませんが、じゃぁ、音楽の先生や家庭科の先生は、月曜日はお休みですか?ということになります。
これも、困ったちゃんですね。
なので、ウチの塾は、対策として、祝日でも休まないことにしています。均等に休みがあれば、不公平も出ませんが、こう、月曜ばかリ休みとなると、祝日だからという理由で休みにはできません。
ですが、中には、祝日は休むことに決めている人もいて、そういう人が、月曜日に来ることになっていると、休みばっかりで、これまた困ったちゃんです。
今でこそ、当たり前になって、それなりの対策ができていますが、変わった当時は大混乱でした。
ということで、誰が幸せになれたのかよくわからないハッピーマンデー。
すでに、死語となりつつあるようですが、そういう混乱もあって、今でも、尾を引いている部分はあります。
参考にしてくだサイ。